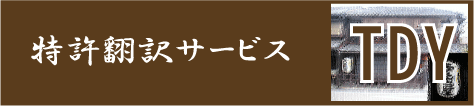|
|
", which(カンマ付き)" は非制限的用法で用い、"that" は制限的用法で用いる、と言われる。 特許の英語表現・文例集 (a) The pen, which is red, is on the table. (b) The pen that is red is on the table. (a)の場合、", which is red,"は「付加情報を加えているだけ」で、これを「除いても文(a)の基本的な意味は変わらな」く、「この場合一本だけペンがある」、と説明されている(詳しくはこの本をお読みください)。 (b)の場合、「たとえば、何本かペンがあるが、その赤いペンだけが机の上にある」、と説明されている。 他の説明の例を見てみよう。工業英検1級対策―文部科学省認定で (a) All the cars, which turned right, are red. (b) All the cars that turned right are red. (a)の場合、", which turnrd right,"を、「取り去っても、文法的にも意味的にも誤りのない文章が残」り、「全車すべて赤かったのである」、と説明されている。(b)の場合、 「左に曲がったり直進していった車のことは知らないが、右に曲がった車はすべて赤かったという意味になる」、と説明されている。 さてさて、特許明細書の翻訳では、どう使い分けるとよいだろう?クレームでは、“除いたり”、“取り去ったり”しても意味が変わらない用法は、通常(あくまで通常)、 用いられないと考えられる。したがって、", which(カンマ付き)"と"that"のどちらかを使うなら、"that"を用いるべきとケースがほとんどだろう。ただ、"(カンマなし)which"を 使っているケースもよく見る。 特許翻訳の基礎と応用 高品質の英文明細書にするために 一方、従来技術に記載されている文章では、", which(カンマ付き)"の方が適している場合があると思われる。 従属クレームの冠詞は、A かThe か? 従属クレームの冠詞は、"The"から始められるケースが多いように思われる。けれども、MPEP 608.01(n) Dependent Claims では、"A"から始める例示ばかりあげられている。 さて、いったい、"A"と"The"とどちらが正しいのか? Landis On Mechanics Of Patent Claim Drafting (Hackett Classics) があげられている。4つの例文中、"The"が3例だ。 特許の英語表現・文例集 私も、従属クレームを"The"で始めています。経験的に、実務上"The"で始めるケースの方が一般的だと考えているからである。"A"と"The"とどちらが正しいのか?なんて、 "A"と"The"の解釈の違いの判例が出るまでわからないのかもしれない。 “請求項1に記載の発明は...”は、"In the present invention according to claim 1, ..."でよいか? 【課題を解決するための手段】欄によく見られる日本文“請求項1に記載の発明は...”を、"Summary of the Invantion"欄の中で訳すとき、"In the present invention according to claim 1, ..." と訳すのは抵抗がある。特許の英語表現・文例集 また、特許翻訳の基礎と応用 高品質の英文明細書にするために さらに、こうした訳仕方の説明として、「日本特許法では独立クレームを発明と呼んでいるために、『第一の発明』『第二の発明』などの表現がしばしば行われます.しかし, 発明が複数あるという表現は発明の単一性の建前から見てもおかしいので,『第一の観点』『第二の観点』と読み替えて翻訳します」と書かれている。 私も、これらに倣い、たとえば、“請求項1に記載の発明は、...を備える装置である”であれば、"A device according to a first aspect of the invention includes ..."等の表現を用い、 さらに、“請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の装置であって、...”との記載があれば、"In a device according to a second aspect of the invention, in the device according to the first aspect of the invention, ..."と訳すようにしている。 |
|
|---|---|---|
| |
||
|
(C) Takuji Terada |
||