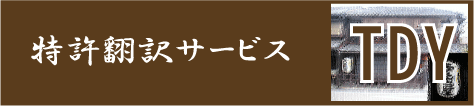|
|
特許請求の範囲(claims)に関する法律の一例 日本特許法 特許法第三十六条(特許出願) 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために 必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。… ((5) The scope of claims as provided in paragraph (2) shall state a claim or claims and state for each claim all matters necessary to specify the invention for which the applicant requests the grant of a patent.) 米国特許法(35 USC) 35 U.S.C. 112 Specification.(second Paragraph) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. 欧州特許法(EPC2000)規則 Rule 43 Form and content of claims (1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. 以上の通り、クレームに記載された文言は特許権の及ぶ範囲を特定します。つまり、特許侵害訴訟で販売差し止めや損害賠償の判決が得られるか否かは、 この文言にかかっているといっても過言ではありません。したがって、クレームの翻訳では、その翻訳した文が、 ・ 特許を受けようとする発明を特定、あるいは ・ particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention, あるいは ・ define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention できているかを、明細書、図面等の記載との整合性の観点から、確認することが重要と考えられます。この確認を可能にするために、翻訳者は、電気、機械、 化学、バイオ等の自分の専門分野のみの翻訳を受任することが一般的なようです。 クレームの書き方について勉強されたい方には、参考になる本として以下の本を挙げておきます。 |
|
|---|---|---|
| |
||
|
(C) Takuji Terada |
||